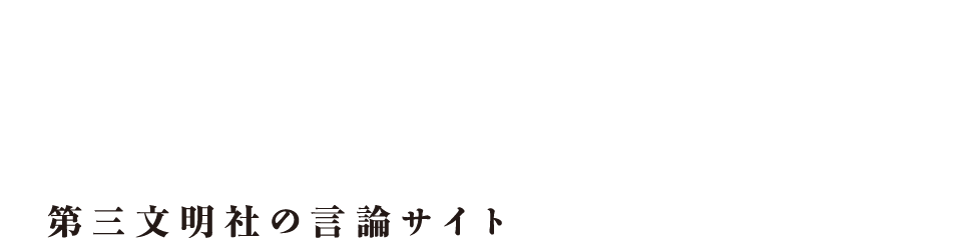5歳にあこがれる54歳。この本から受けるのは、茂木さんのそんな本質だ。
初々しさや純真さへの郷愁(ノスタルジー)もあるが、それだけではない。肩書も役職もなく、その刹那に没頭する裸一貫の「今、ここ」に対する敬意と慈しみが、そのあこがれを支えている。大人にとっても自立とはそのようなものだし、そのようであるべきだという考えが、そのあこがれを支えている。だから、コースから外れて人生の不安を感じざるを得ない「ぐれたやつら」に共鳴したり、海で泳ぐのが怖いくせに、人生はプールのようなコース・ロープのない海を泳ぐように生きていきたいと表明したり、「キャンバス上の手の動きがすべて」の画家を、権威をコテコテに身にまとわないと生きていけない独裁者と比して称揚したり、拡声器なしに「無闇に声を張り上げる」選挙演説中のヤジに感心したりする。人生の記憶を思い出すままに書いたエッセーでありながら、やはりそこには茂木健一郎という科学者の「人と思想」が色濃く反映している。
また茂木さんは、何でもない穴を「クマの穴」だと大騒ぎした小学生時代を思い起こして、こうも言う。
それを、『クマの穴』だと一瞬でも本気で信じた、あの頃の生のあり方に、これからの時代のヒントがあるように感じられる。(P43)
と。そう、問題は「生のあり方」だ。
茂木さんは、刹那の自由を謳歌すればそれでよしという無頼漢ではない。自由が常に不安とセットであることを痛感しつつ、それでもなお、何かを本気で信じてみるその一歩に、「こざかしさ」の対極にある生の希望を見る。それは、タイトルにある「春」を象徴する満開の桜に「どうしたらいいかわからなく」なりながら(桜の木の下には死体が埋まっている!)、それでも「屍を乗り越えて横溢していく」生を肯定するところに通じていく。
茂木健一郎とはそのような人だなあ、と彼以上に彼を感じさせてくれる一冊だ。